背の低さに惹かれてAnker Nano II 65Wを使い始めて3日。
1ポート出力で足りるか、使い勝手を検証していたところ、思いがけないところで課題が発生しました。。、
いきなり増えたACアダプターの忘れ物
最近、ACアダプターをコンセントに挿したまま、忘れてきてしまうことが増えました。
不思議なことに、最新の小型アダプターに買い替えてからの出来事でした。
ここ2日で3回の置き忘れ
我ながら情けないのですが、ここ2日で実に3回もやってしまいました。
一度目は自宅のコンセントに。二度目は職場の自席、そして三度目はカフェです。
幸い三度目のカフェでは店を出てすぐに気づき席に戻りました。
しかし一度目と二度目は気づかず、外出先で電池残量と戦いながら仕事するはめになりました。
突然連発、、、なぜ?
これまで何年もノートPCとACアダプターと共に過ごしてきましたが、こんな経験はありません。
きっかけは、Ankerの名機「Nano II 65W」に買い替えたことでした。
USB-Cポートが1つだけの、非常にコンパクトな製品です。
仕事が立て込んでいて、急いでいたのも確かですが、これまでのガジェットライフでは考えられない事態です。
なぜ小型ACアダプターは忘れられやすいのか?
この現象について、管理人なりに原因を分析してみました。
どうやら、アダプターの「小ささ」そのものが、このうっかりを引き起こしているようです。
いくつかの要因が、絶妙に重なっている気がします。
原因1:あまりに小さく、軽すぎる「存在感」
最近の小型ACアダプターは、本当に小さくなりました。
純正品と比べると、体積も重さも半分近くに感じます。
壁のコンセントに挿した姿はとてもスマートです。
しかしそのスマートさが、かえって意識から抜け落ちやすくさせているのかもしれません。
この「存在感の希薄さ」が、忘れ物の大きな原因だと感じています。
原因2:ケーブル1本だけという「意識の死角」
PCを片付ける際、本体からUSB Type-Cケーブルを引っこ抜けば、それで満足して「はい次!移動!」となっていました。
ケーブルが1本だけだと、コンセント側にある親玉の存在まで意識が届きません。
人間の注意力、ワーキングメモリーの限界というより、仕事が立て込んでいたという状況のせいかもしれません。
つまり、急いでいるときは主要なタスク(PCをしまう)のみに意識が向き、付随的なタスク(アダプターを抜く)が抜け落ちてしまうことがあるのです。
複数ガジェットの同時充電が「リマインダー」になっていた説
ふと、忘れなかった時期のことを思い出しました。
それはPC用の充電と同時に、3-in-1ケーブルでスマホやイヤホンも同時に充電していた時です。
複数のケーブルがアダプターから伸びている光景は、物理的にかなり目立ちます。
「あれもこれも抜かないと」という思考が、皮肉にも安全装置として機能していたのでしょう。
存在感あるACアダプターによる複数のガジェットへの充電という行為が、結果的に忘れ物防止のリマインダーになっていたようです。
ACアダプター選びの新たな視点
今回のほろ苦い経験から、ACアダプターの選び方そのものを考えさせられました。
性能やサイズはもちろん重要です。
しかし、それだけを見ていると、思わぬところで足元をすくわれるようです。
「小ささこそが正義」とは限らない
ガジェット界隈では、よく「小ささは正義」と言われます。
管理人自身もそう信じて、常に最小・最軽量のモデルを追い求めてきました。
しかし今回の件で、「小ささこそが正義」とは限らないと痛感させられました。
利便性を追い求めた結果、PCがただの重い板になってしまうのは、あまりにも悲しいですから。
小型化の弊害?発熱やスペックの問題点
最近、あるメーカーの卵ほど小さい高出力アダプターが話題になりました。
その製品は、圧倒的な小サイズと携帯性が評価される一方、高負荷時のかなりの発熱が指摘されています。
人によっては不安を覚えるほど熱くなり、安全機能で定格の65Wよりも出力が落ちることもあるようです。
これも、小型化だけを追求することの難しさを示しています。
スペックシートの数字だけでは見えてこない、行間のリスクとでも言うべきでしょうか。
忘れ物対策としての「存在感」という性能
そこで管理人が提案したいのが、「存在感」という新たな性能指標です。
それは、適度に大きく、適度に重く、視界の隅で「ここにいるぞ」と知らせてくれること。
あえて少しだけ無骨な製品を選ぶことで、忘れ物のリスクを減らせるかもしれません。
まるで番犬のように、そこにいることを知らせてくれる。
そんなアナログな感覚が、実はハイテク時代にこそ必要なのかもしれません。
先に述べた発熱(排熱効率)や出力安定性も一定の表面積あってこそですしね。
まとめ
最新の小型ACアダプターは、技術の進歩を肌で感じさせてくれる素晴らしい製品です。
しかし、その進化の過程で、私たちは何か大事な感覚を置き去りにしているのかもしれません。
性能やサイズだけでなく、自分の使い方に合った「存在感」で選ぶ視点も意識すべきだな、と思いました。
ガジェットとの付き合い方は、まるで人間関係のようですね。管理人には存在感があっても4ポートのUGREEN Nexode 65W X599ほうが相性がいいのかもしれません。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
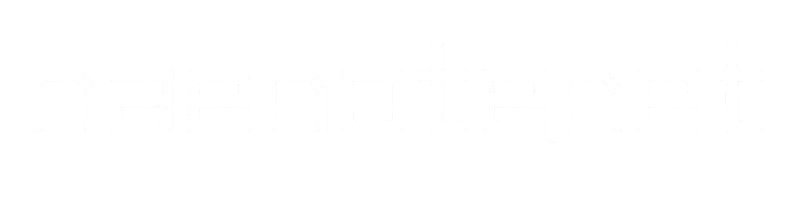

コメント