以前組み立てたcool642tbをロープロファイル軸に換装してみました。
結果、意外と違和感なく使えそうとわかり、かつ、いろいろ世界が広がりそうな感じです。
一部始終を紹介します。
なぜ今、ロープロ化に挑んだのか?
これまでMX軸のキーボードを愛用してきました。しっかりとした打鍵感も、キーが深く沈む感覚も気に入っています。しかし最近、ある思いが頭をもたげてきました。それは「もっと身軽に出かけたい」という純粋な気持ちです。
愛機「roBa」のかさばりが気になり始めた
きっかけは、以前に組み立てた自作キーボード「roBa」です。トラックボールを搭載した分割キーボードで、操作性は文句なしに快適。ただ一つ、持ち運ぶには少しだけかさばるのが悩みでした。
3Dプリントで作られたケースの構造上、どうしても厚みが出てしまいます。日々の相棒だからこそ、この点がどうしても気になっていました。もう少しスリムにならないものか、と考えるようになったのです。
スリムさを極めたらどうなる?という探求心
そこで思いついたのが、キーボードのロープロファイル化でした。キースイッチ自体の背を低くすれば、劇的に薄くなるはずです。幸い、手持ちの「cool642tb」なら、それが可能な設計でした。
もちろん、慣れ親しんだMX軸の快適さを手放す不安はありました。しかし「逆にスリムさを極めるとどうなるのか」という探求心が、最終的には勝利しました。こうしてcool642tbのロープロ化に着手することにしたのです。
cool642tbのロープロ化・換装作業
実際の換装作業は、想像していたよりもずっとスムーズでした。コーヒーを飲みながらのんびり進めて、約1.5時間で完了です。ここでは、その手順と準備したものについて解説します。
ロープロ化のために用意したもの

今回は特に急ぎの作業ではなかったこともあり、AliExpressのセールを利用して部品を買い集めました。汎用品はまとめ買いしておくと、後々また別の沼にハマった時に便利です。
かかった費用は、総額でだいたい5,000円くらいでした。
急ぎでなければ、こうした部品は海外通販サイトのセールで安く揃えるのがおすすめです。
Choc用ソケットのはんだ付けが最初で最後の関門
cool642tbの基板(PCB)は、少し面白い設計になっています。一般的なMX軸用と、ロープロファイルなChoc軸用の両方のソケットを付けられるのです。
今回は、用意したChoc用のホットスワップソケットをはんだ付けしていきます。なお今回の作業で、はんだごてが登場するのはこの工程だけ。ここさえ乗り越えれば、山場は越えたようなものです。
というか、初回の組み立てと比べるとチョイでした。
ネジとスペーサーの工夫で理想のスキマ感を追求
ソケットを実装したら、あとは組み立てるだけです。トッププレート、基板、ボトムプレートの3枚を重ねて固定していきます。ここで、全体の薄さを決定づける、重要な一工夫を加えました。


公式のビルドガイドでは、基板とボトムプレートの間に3mmのスペーサーを入れるのが標準です。しかし今回は薄さを極めるため、そのスペーサーを使いませんでした。代わりに、以下の方法で固定しています。
- トッププレートから8mmのM2ネジを通す
- ボトムプレート側をM2ナットで固定する(なんとちょうど凹み部分にフィットするんです)
これにより、基板とボトムプレートの隙間を3mmから2mmにまで圧縮できました。このわずか1mmを削るための追求が、最終的な本体の薄さに大きく貢献してくれるのです。この微調整が、地味ながらも完成度を左右する大切なポイントでした。
徹底比較。MX軸仕様から何が変わった?
さて、ロープロ化によって使用感はどう変わったのでしょうか。管理人自身、期待と不安が入り混じっていました。ここでは以前のMX軸仕様の時と比べて、何がどう変わったかを正直にレビューします。
体積は3割減。カバンの中身が驚くほどスッキリ


まず、最も期待していた携帯性です。これは期待を大きく上回る、素晴らしい結果でした。キーボードの厚みがグッと圧縮されました。
もとの7割くらいにはなったでしょうか。


roBaと比べるとこの通り。上から見た面積はほぼ同じでも、厚みはだいたい3分の2程度に。
この薄さはMX軸ばかり使ってきた管理人にとって革命的です。

休日用の小さなショルダーバッグでも余白ができてスッキリ。持ち運ぶガジェットが一つ減ったかのような身軽さです。
仕事カバンのかさばり解消にも効きそうですね。
肝心の打鍵感は?「ペチペチ感」を回避できた理由

とはいえ、毎日使うキーボードの打鍵感が悪ければ意味がありません。以前ロープロ軸を試した時は、正直「ペチペチ」とした軽い感触が好みではありませんでした。
今回はその反省を活かし、事前に試打を重ねてスイッチを選びました。結果、「Kailh Deep Sea Silent Mini」という静音リニアスイッチを採用。これが大正解でした。
このスイッチは、ロープロにしては押し込める深さが少し確保されています。そのためか、安っぽい底打ち感がなく、とても上品な打鍵感です。静音性も高く、愛用のMX軸スイッチ「Outemu Silent Peach V3」と比べても遜色ないレベルの静けさでした。
操作性:キーの遠さと手首の角度の変化

キーボード全体の高さが変わったことで、操作性にもいくつか変化がありました。良くなった点と、少し慣れが必要そうな点が見えてきます。
- 手首の角度: キーボードが低くなった分、手首をあまり曲げずに自然な角度で打てます。これは地味に楽なポイントです。
- トラックボール: ボールの高さは変わらないため、操作感はMX軸の時とほとんど変わりません。違和感なく移行できました。
- キーの距離感: キートップが平たくなった影響かもしれません。四隅のR2キー(YTQP)が、ほんの少し遠くに感じることがありました。これはキーボードの位置や角度の調整でカバーできる範囲です。
使って見えた、新たな課題と次への道

全体的には大満足のロープロ化でした。しかし、人間とは欲深いもので、使っているうちにもう少し改善したい点も出てきました。完璧なものはなく、常に次のカスタマイズの種が見つかるのも、自作キーボードの面白いところです。
打鍵時に手のひらがトラックボールケースに触れる
ロープロ化でキーボード全体がグッと低くなりました。その結果、トラックボールを収めているケース部分が相対的に出っ張る形になります。タイピング中に、この出っ張りが手のひらの付け根あたりに触れることがありました。
実用上、大きな問題というわけではありません。しかし、収納時にもこの出っ張りが少し気になります。どうにかして、もっと全体をフラットにできないかと考え始めてしまいました。この探求は、終わりがありません。
次の沼?14mmボール埋め込み型へのあこがれ
この「手のひら問題」を解決するヒントは、他のキーボードにありました。それは、14mmの小さなトラックボールをキーの間に埋め込んでしまうタイプのキーボードです。「LineA40」や「Conductor」といったモデルがそれに当たります。
これらのキーボードなら、手のひらがケースに触れる悩みは根本的になくなります。薄さと操作感を両立する、次なる理想の形かもしれません。新たなキーボード沼が、すぐそこに口を開けているのを感じます。
まとめ
今回の挑戦は、個人的にとても大きな収穫でした。正直に言うと、これまでロープロキーボードを少しだけ敬遠していました。しかし、それは単なる食わず嫌いだったようです。
スイッチをしっかりと吟味すれば、打鍵感は十分に満足できるレベルに到達します。そして、それと引き換えに得られる携帯性の向上というメリットは絶大です。自分の中の選択肢が増えたことが一番の喜びです。
これからはMX軸もChoc軸も、その日の目的や気分に応じて使い分けることができます。
食わず嫌いはもったいない。ロープロは新しい選択肢になる。これがわかったので、これからの自作キーボードライフが、また一段と楽しくなりそうです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
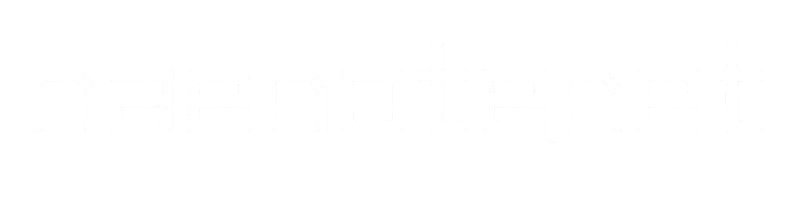

コメント